前時の学習終了時からキーナンバーの読みを試みていた子ども達は、すぐに読めた。「7936」と宝箱のカギに入力するパフォーマンスをとり、手元に隠しておいたベルを「チーン」と鳴らす。おもむろに箱を開け、中を見て「おーっ」と驚いてみせる。「いっぱい入っている。」と言いながら、箱の中に入れておいた本時学習に必要なものを取り出す。全部出した後に、箱の底の方に「第2の問題を解いて第2の箱を開けましょう」と書いてあることを告げる。そして子ども達に問題を提示した。子ども達には問題文と同じプリントを配布する。
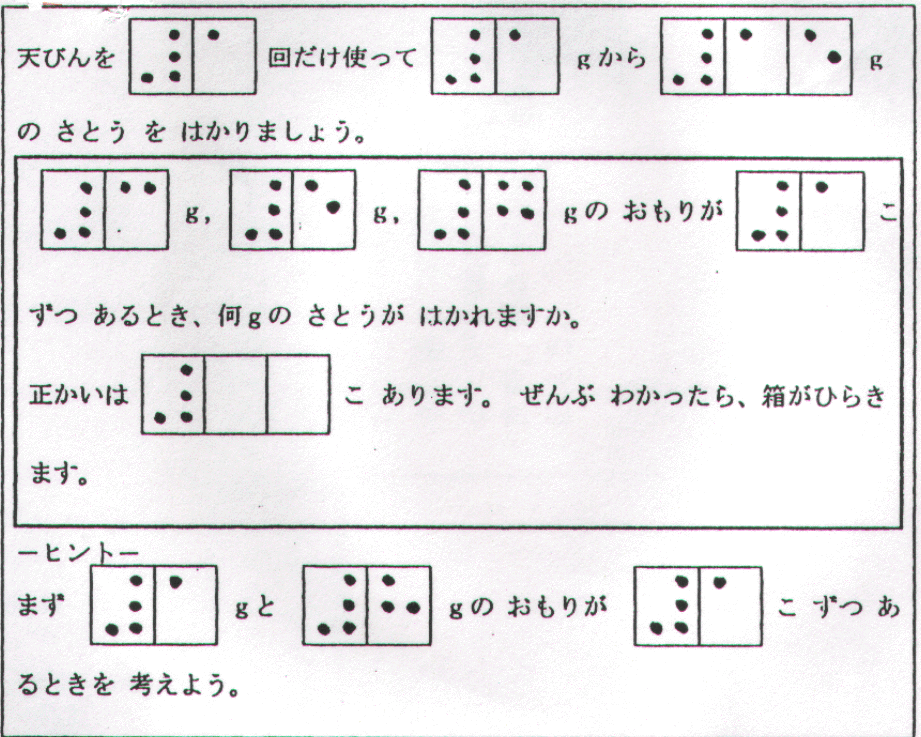
(C)Two-Way/トスランド/小学校/算数/第4学年〜第6学年/
|
|
広島県福山市立水呑小学校 教諭 粟村啓史
「点字と算数」の第2時。前時の学習で「0」から「9」までの点字の数字が全部わかった、というところから本時をスタートさせた。
[尚、本時授業は、広島県算数・数学教育研究(福山)大会で行ったTTでの公開研究授業(注1)である。]
まず、前時で学習した点字の数字と宝箱の「キーナンバー」を提示しておく。
|
|
|
|
(発問1) キーナンバーは、どう読めばいいのですか。 |
と、発問する。
前時の学習終了時からキーナンバーの読みを試みていた子ども達は、すぐに読めた。「7936」と宝箱のカギに入力するパフォーマンスをとり、手元に隠しておいたベルを「チーン」と鳴らす。おもむろに箱を開け、中を見て「おーっ」と驚いてみせる。「いっぱい入っている。」と言いながら、箱の中に入れておいた本時学習に必要なものを取り出す。全部出した後に、箱の底の方に「第2の問題を解いて第2の箱を開けましょう」と書いてあることを告げる。そして子ども達に問題を提示した。子ども達には問題文と同じプリントを配布する。
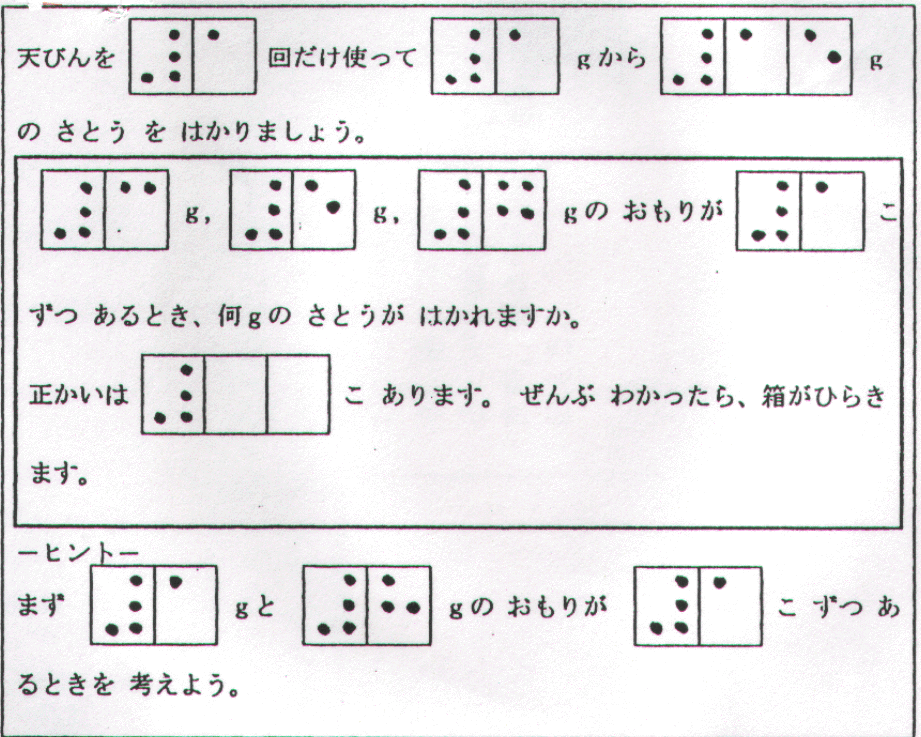
(指示1) 一カ所だけ何も書いてないところがあります。そこは何も書かなくてよろしい。 それ以外の点字の部分を全部普通の数字に書き直しなさい。全部書けたら 起立。 |
上記の問題は、「大阪書籍小学算数4年上P.22」から引用した。ここは、教科書では一学期に学習することになっていたが、4年生の天秤の学習との関連から、また、思考を促す良き問題であるとの判断から、この時期の「点字と算数」の学習題材とすることにした。また、一カ所何も書いてないところを作ったのは、点字のマスが2つあることから二桁の数であり、最低でも10個はあるんだということを認識して欲しかったためである。
さて、全員が起立した後、全員で問題文を読んだ。黒板に掲示した問題文には、T2が赤マジックで点字の数字の下に普通の数字を書き込んでいった。
その後、子ども達に「天秤を一回だけ使う」ということの意味をはっきり認識させることを目的に、実際に天秤を使って5gの塩を量りとって見せた。そして、「天秤を一回だけ使う」とは、小刻みではなく、一気にやってしまうということであることを説明した。また、「釣り合ったら等しい。」ということも押さえておいた。
その後まずヒントの問題を通して、考え方ややり方の基本を確認させた。
(発問2) 1gと8gのおもり1個ずつでは、何gがはかれますか。 |
まず9gという意見が出た。「どうやって量りますか。」と問うと、
・1gと8gを左側において、砂糖を右側におく。1gと8gを足したら9g。と答えた。黒板で、紙で作った分銅と砂糖を 使って操作して見せた。その後、「今のを図に書いたらこう書きます。」と言って図の書き方を教え、「式に表した らこう書きます。」と言って式の書き方を教えた。
「もう他にありませんか。」と問うと、「1g」「8g」と答えた。同様に図の書き方を教え、式には書けないので「1g→ 1g」「8g→8g」と書くように教えた。さらに「もう他にありませんか。」と問うと、「7g」と答えた子がいた。「どうやっ て量りますか。」と問うと、
・8gを左側に置いて、1gと砂糖を右側におく。砂糖は1g減るから7g。
と答えた。黒板で、紙で作った分銅と砂糖を使って操作して見せた。その後、同様に図の書き方と式の書き方を 教えた。
そして、「今日挑戦する問題は、太い四角の中の問題です。」と、今日の学習課題を確認した。
(発問3) 何グラムのおもりが使えるのですか。 |
使えるおもりは、「3g」「5g」「7g」の3つだけであることを押さえた。そして、この3つのおもりを使って1gから15gまでのどのグラム数が量れるか、どうやって量るのかを考える問題であることを確認した。そして、その後約10分間、各自自力解決に挑戦させた。
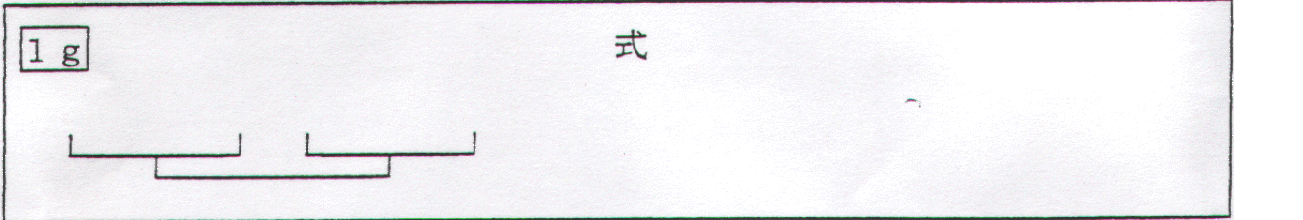
上のような書き方で、1gから15gまでをそれぞれ考えさせた。左側には操作の図、その右側には砂糖のグラム数を式表現する。
子ども達は、最初はよく分かっていないようで、何となくピンとこない感じだった。T1T2で個別指導を続けた。全体の様子を感じながら、ときたま私が全員に説明の言葉を発した。「足し算で考える。」「ひき算で考える。」の両方の考え方があることを確認し、その両方の考え方を上手に使うように促した。発表はあまり期待できないかもしれないなと思いながら、約10分後、「黒板に出て書きたい人はどうぞ。」と言ったら、期待以上にたくさんの子が前に出て書いていた。
その後、発表活動。黒板横に白ボードを置き、紙で作った分銅と砂糖を使って量り方を操作させながら発表させた。
「6g」「11g」「13g」「14g」以外は全部量れる。量れるグラム数は全部で11個あったことになる。子ども達に再度確認した。間違いないという。
第2の箱にその11個をインプットするパフォーマンスをとり、手元に隠しておいたベルを「チーン」と鳴らし、第2の箱が開いたことを告げた。
第2の箱を開けると、第3の箱とメッセージ。
第3の問題に挑戦し、第3の箱を開けましょう。 −ルポン8世− |
というメッセージ文を添えておき、次時に第3の問題に挑戦することを告げた。その後、数名の子に授業の感想を述べさせてこの日の授業を終えた。
子ども達からは、
・たった3個のおもりで11個も量れるので、すごいなと思った。
・いろいろ考えたので楽しかった。
・次の時間の第3の問題が楽しみです。
という感想が出されていった。
(注1)指導案紙面では、「T1粟村真之」となっているが、「粟村真之」は「粟村啓史」と同一人物である。
・表紙へリンク ・第1時へリンク ・第3時へリンク
TOSSランドへ メールはこちらから
(C)TOSS Awamura
Hirofumi All right reserved.